外断熱・壁構造のRCマンションになったわけ(7)
海大好き⇒ボート造りバカに(プロフィール7)
多摩川の傍に越してから、海好きが高じて、ボート造りに夢中になったのですから何としても完成したい。
木製ボート造りは、材木の強度と比重の関係や、木材の部分的特性などの知識が付き、そして「自分で住みたい家」は
木造住宅から鉄筋コンクリート住宅へと移って行くことになります。
木材は古来から人の建築材料としては基本的な材料で有ったのは間違いありませんが、石造りの多いヨーロッパにし
ても何でもかんでも石造りばかりでは無く、他の地域では圧倒的に木造の家です。
日本では山岳が多く、材木の種類もいろいろ有ったので、木造建築の巨大な建造物が沢山有りますが、長年の間には
補修しての話です。
木材で何か作ろうとすると、直ぐに木材の奥の深さに驚きます。
木は山に生えていますが、山の東西南北どの位置に生えていたか、山肌の傾斜の違いまでもが、木材の性質に関わ
るということを知ります。
ボートというものは、船の形をなす外側を船殻といいますが、その船殻自体が船の強度の大半を担うといっても大間
違いでは無いほどですが、それは荒天の時に何メートルもの高さから水面に叩き付けられるのです。
そうした過酷な条件に耐えなければ船としては通用しません。
そうしたことから、船殻全体が少しづつ歪んでショックを吸収することが解っています。
それは、船殻が殆ど真っ直ぐでは無く、曲がっていることによるものです。
陸上の建築物も曲がっていれば非常に強い筈ですが、使い勝手はかなり犠牲になるかも知れません。
しかし、外洋を走るヨットを知る方達には問題無いと思いますが。
福井地震後に、学校で「地震に強い家を考えて絵をかきなさい」という授業で、かなり多くの生徒が丸いボールの様な
家を描きましたが、住み心地はどうかと思った記憶があります。
そこで、木造やRC(鉄筋コンクリート)では中低層、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)や鉄骨造りでは、軸組構造基本であ
りながら、接合点の頑丈さと全体の柔軟性から高層ビルに使われていると理解しています。
近年では、より柔軟な構造にして長周期振動の地震に耐えられることを目指し、免震などの装置との組み合わせなどを
研究していると思われます。
プロフィールは今回で終わります。
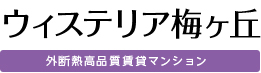

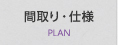
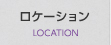
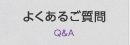



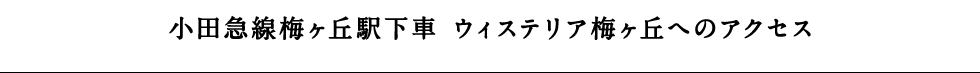
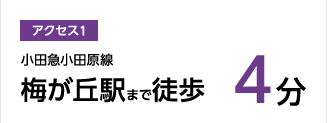
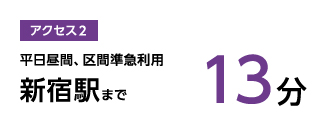
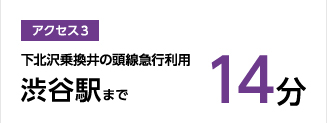
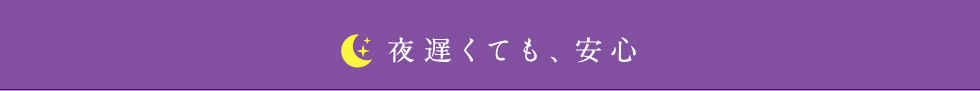
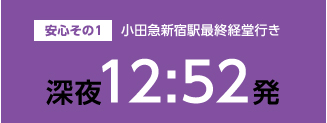


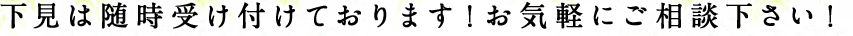



トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.wisteria-umegaoka.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/31