竜巻で屋根が飛んだ時
竜巻で屋根が飛んだ時 外断熱壁構造のRCマンションになったわけ(19)
以前、 多摩川の近くに居た時、台風の夜に、木造二階建ての住宅の屋根が全部飛んだ事があります。
風の音が激しく、ほんの少し前までは有った筈の屋根が無く、停電ですから真っ暗ですが、階段を登ろうと上を向いた
時に何故か白っぽいものが動いています。 何だろうかと上がって見て、それが雲だった事が解りました。
そして、その屋根は何と、30m位も飛んで、天井付けの蛍光灯まで付いたままです。
朝になって、建築事務所の方達が来て見たところ、小屋裏(屋根と天井の空間)との堺に有る太い梁が折れていて、
とてつもなく大きな力が掛かった事が判りました。
非常に小型の竜巻だった様で、家並みとは斜めの方向に被害の有った家が転々としていますが、ほんの少し離れた隣
家は何とも無いのですから、とても情けなくみじめな状況でした。
当時は、現在の様に大規模竜巻は無く、小規模でしたが、かなりの威力です。
米国の竜巻の跡を見ても、木造家屋は殆ど破壊されていますから、竜巻を考えると木造家屋、それも在来工法の家屋
では太刀打ち出来ないということになります。
築10年位のその家は折れた木材の材料を見ても、かなりしっかりしていて、手抜き工事とか、材料のせいでは無いこ
とが判ります。
二階の部屋には、雨戸も有り、台風の時は閉めてあったののですが、雨戸ごと吹き飛んで、風が室内に入り、屋根の
小屋裏に天井を付けたまま飛んで行ったのでしょう。
阪神淡路の震災では、鉄骨造りの3~5階建て位のビルは一階が崩壊している事が多く、H型鋼がぐにゃりと曲がっ
たり、溶接部分から外れたり、アンカーボルトが破断していたりと、様々ですが、鉄骨作りの溶接に関する施工不良は
以前にも新宿の大きな建物で問題になった事があります。
その時は、溶接部分の処理ですが、開先(かいさき)といって、溶接部分の面を斜めに削って溶接しなければならないと
ころ、隅肉溶接といって加工しない材料をそのまま現場でアーク溶接(電気溶接)して居たというのですが、神戸の場合
もそういう工事が多かった様です。
こうしてみると、外観からは判らないけれど、紙一重で倒壊するか、残っているかが決まる様で、きみが悪くなります。
どんなに立派な設計士が立派な設計をしても、施工状態が建物の物理的特性を決めてしまうからです。
殆どの設計事務所は設計監理とうたって、施工監理を入れた計算価格になっていますが、本当に何処まで見ているか
は大いに疑問視出来ると思うからです。
昔は、コンクリートの配合も目を光らせていないと、間違った配合のコンクリートが来ると聞いた事があります。
現場監督の仕事になっていますが、設計士はデザイナー的存在で、現場を直接見る事は少ない様です。
たまに、現場を見に来た設計事務所の人に、こんな型枠どうやって作るんだよ!と噛み付いている職人がいましたが、
最近はどうでしょうか。
とかく設計士は奇抜なアイディアや奇抜な外観を好んで、建築家が良く見る雑誌に載るのを期待するそうです。
確かに新しい時は綺麗で洒落ていても、十年以上経った時どうなるか?
手入れに大変な銘木を多用したり、直ぐ染みになる材料をつかったりと、お金を払う施主が困るのはずっと後の話です。
極端な例ですが、チーク材などを長く使うと本当はチークオイルを何時も塗っていないと汚くなりますが、そこいらに
売っているチークオイルは、殆ど全部が人工的に合成された物で、塗るとかえって黒くなり、汚く見えてしまいます。
亜麻仁油は耐候性が抜群で、外で使用する木材に塗ると物凄く長持ちします。
木造船に亜麻仁油を塗っていた昔の船が米国で発見され、100年以上経っている事が判った事があります。
何十年も前ですが、塗料の専門店に天然の亜麻仁油が欲しいと言ったら、「お客さん、今日本にどれだけ輸入されて
いるか知っていますか? 年間ドラム缶三本もどうかと言う位ですよ!」と叱られてしまいました。
人が直接目にしたり、触れたりする場所に木材を使うと、確かに落ち着いた感じになりますし、湿度も適当に調整
する働きが有ったりして具合の良いものですが、この木材が問題なのです。
ある家の新築中を見せて貰った時の事ですが、その工務店は元々材木屋なので、良い木材を使っていると鼻を高く
して説明して呉れました。
確かに柱の太さや材料の大きさは建売の物とは違うことが判りますが、触ってみるととても冷たく、明らかに乾燥の
不充分な材料を使っています。
そんな柱に幾ら金具を使って、梁を固定しても、どれだけ効き目が有るか疑問です。 乾燥と共にヒビが入り、金具
を止めた釘はどれだけ効き目が有るのか怪しいものです。
材木は普通、山から切り出して、皮をむく前に5年位は寝かせておいて、それから製材して又乾燥しますので、
かなりの時間を掛けます。 家具などの精密加工品の材木は20年は乾燥するそうです。
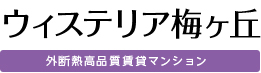

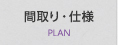
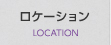
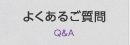



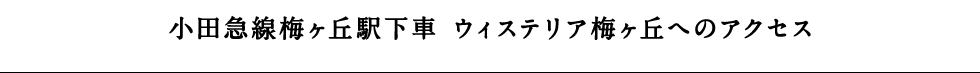
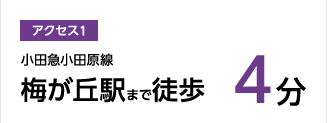
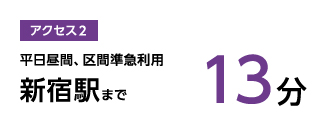
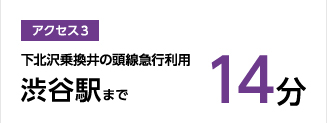
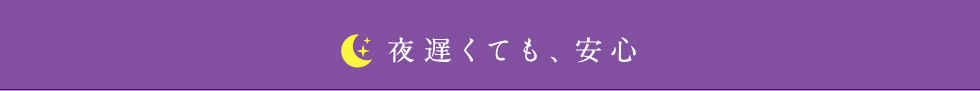
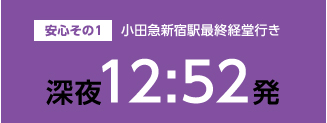


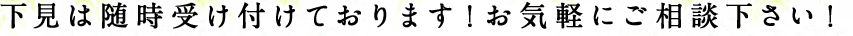



トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.wisteria-umegaoka.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/39